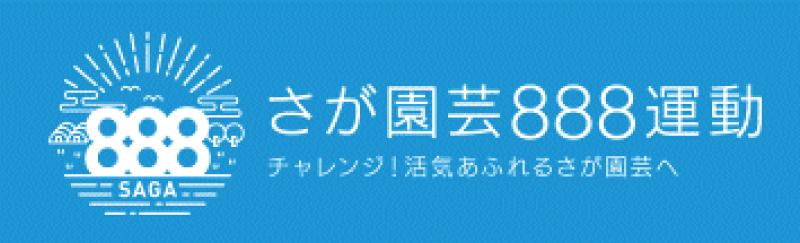費用に関すること
いちご農家への新規就農にチャレンジしたい相談者の方から、いちばん多いお問い合わせ内容はお金に関するご相談です。いちごを育てるには専用のハウスや暖房器具、出荷調整小屋や冷蔵庫など、さまざまな設備が必要で多額の資金が必要になります。
このページでは、JAさが白石地区いちごトレーニングファームを卒業して、新規就農するときに必要になるお金のこと、少しでも初期費用を減らすための補助金や助成金の情報を併せて掲載します。
※この情報は2024年5月時点の情報になります。
いちご農家になるためにかかるお金
いちご農家になるために、必要な資金は多岐にわたります。ここでは、新規就農するときに必要になる設備の紹介と、設備を購入するときの大まかな予算をご紹介していきます。
※10aの農地を基準に予算を掲載しております。
設備投資にかかるお金
-

パイプハウス
いちごは品種によって差はありますが、春頃の気候を好む傾向があります。栽培環境の温湿度を管理するため、パイプハウスは必ず必要となります。
適切な管理を行う事で、品質を揃え、収入を確保することができます。およそ900万円
の費用が必要になります。
-

育苗用パイプハウス
育苗用パイプハウスとは、イチゴの株を定植前まで育てるために利用するハウスの事です。苗作りは定植後の収量に大きく影響するため、苗の適切な管理を行うために必ず必要な設備になります。
写真にある架台のように病気を抑えるためにも設備が必要になります。およそ600万円
の費用が必要になります。
-

井戸の掘削、配管工事
農業用に利用する水は、井戸水、水路の水が一般的です。しかし、水路の水では環境により水質が大きく変化し、水道水では高額になるため、井戸水を推奨しています。
井戸は掘削作業、利用するための配管工事も必要になります。およそ300万円
の費用が必要になります。
-

高設栽培
いちごを定植する高さを地面から1m程度上げるための設備です。土壌は培養土を利用し、養分は肥料を主体に調整します。
高さを上げることでかがむ必要が無く、体の負担を軽減できることで、作業効率の向上が見込めますが、経費が高く初期投資が高額となってしまいます。メリット
- 作業がしやすくなる
- 土壌環境に左右されず収量が安定する
- 土壌感染症のリスクが少ない
デメリット
- 施設建設費用が高くなる
- ランニングコストが高い
- 気候変動の影響を受けやすい
およそ3,000万円
の費用が必要になります。
-

土耕栽培
ハウス内で地面にいちごを植えて栽培する方法です。高設栽培に比べ、施設費用が大きく軽減できますが、イチゴを栽培するために土づくりからのスタートとなります。
土が緩衝材となり、肥料成分、温度等の上下は緩やかになる傾向がありますが、土壌病害の拡大には注意が必要で、土壌病害抑制のため、栽培前の土壌消毒が必要です。メリット
- 施設建設費用が高設栽培より安い
- 気候変動の影響を受けにくい
デメリット
- 給液や廃液の管理ができない
- 天候による培地の水分管理が難しい
- 作業姿勢が低く、腰や足への負担が大きい
- 土壌病害に対し、栽培前の消毒が毎年必要になる
およそ730万円
の費用が必要になります。
-

電気工事
いちごを効率的に育てるため、電照工事や、パイプハウス内に設置することで、人為的に日照時間を長くすることができます。
暖房器具と合わせて利用し、光合成を促し、低温によるいちごの休眠を抑える効果があります。およそ630万円
の費用が必要になります。
-

予冷庫
収穫、出荷調整したいちごを品質を保持、保管するために必要になります。
全ての収穫量を保管するため、最大収穫量を基に予冷庫の面積を計算する必要があります。およそ150万円
の費用が必要になります。
-

作業小屋
収穫したいちごの選定、パック詰めを行うため、必要になります。出荷資材の保管も兼ねて行う場合が多く、移住する場合は家とハウスが離れる事もあるため、移動に時間がかかる場合は選択肢のひとつです。
およそ350万円
の費用が必要になります。
-

運送車両
農業資材、収穫物の運送などに必要です。使いやすさ、活用の幅から軽バン、軽トラックを利用する場合が多いです。
※軽トラックを新車で購入する場合の金額です。およそ200万円
の費用が必要になります。
-

動力噴霧器
動力噴霧器は、液体を加圧して圧送し、農薬を噴霧するために使う機械です。噴霧器を使うことで、全体に薬剤をかけることができ、病気や害虫を防ぐことにつながります。
※機器によって異なります。推奨機器の新品購入価格です。およそ50万円
の費用が必要になります。
-

畦立機
土耕栽培時にいちごを定植する畦を作るための機械です。いちごの畦は高さが必要なので人力での作業はとても負荷が高く重労働になります。土耕栽培を行う方は購入を推奨しています。
※機器によって異なります。推奨機器の新品購入価格です。およそ40万円
の費用が必要になります。
-

収穫用コンテナ、台車、ラップ機
いちごを収穫し、出荷するときに利用するコンテナや台車、ラップをかけるときに利用する道具です。
※自動ラップ機を購入する場合の合計金額です。およそ250万円
の費用が必要になります。
-
パイプハウス
900万円
-
育苗用パイプハウス
600万円
-
井戸の掘削、配管工事
300万円
-
電気工事
630万円
-
高設栽培 ◆
3,000万円
-
土耕栽培 ◆
730万円
-
予冷庫
150万円
-
作業小屋
350万円
-
運送車両
200万円
-
動力噴霧器
50万円
-
畦立機
40万円
-
収穫用コンテナ、台車、ラップ機
250万円
- ◆はどちらでいちごを育てるかにより選択します。
※掲載している金額は目安です。
※10aの農地を基準に予算を掲載しております。
| 合計 | およそ 4,200万円(土耕栽培) ~6,470万円(高設栽培) |
|---|
いちごを育てるときにかかるお金
-

定植苗の親株
定植株の親株は、基本的に購入ではなく、自家苗を増殖させ、1つの親株から10本程度定植株を作ります。ただし、病気の抑制、健全苗の増殖等の目的から、2~3年間隔でウイルスフリー株を購入する事を推奨します。
およそ15万円
の費用が必要になります。
-

肥料
いちごに与える肥料は液体肥料と固形肥料があります。必要になる養分は用途により異なりますが、窒素、リン酸、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどがあり肥料を与えるタイミングも重要になります。
およそ20万円
の費用が必要になります。
-

農薬
いちごが病害虫にかからないように、また病害虫にかかったときに治すために農薬を使います。いちごの代表的な病害虫として、うどんこ病、灰色かび病、ハダニ、アザミウマなどがあります。被害が甚大になると収量が激減するため、適切な対策を施す必要があります。
およそ20万円
の費用が必要になります。
-

光熱費
栽培環境の温度を安定させるためのA重油、電照に使用する電気代の経費です。
およそ170万円
の費用が必要になります。
-

定植苗育苗用土
いちごの苗を定植する前の段階で育てるために必要な土になります。
およそ30万円
の費用が必要になります。
-

ミツバチレンタル
いちごの受粉を助けるためにミツバチが必要になります。ミツバチは養蜂場からレンタル、もしくは購入したものを飼育して毎年使います。
およそ20万円
の費用が必要になります。
-

人件費
摘果やラップ作業時に人手が必要になります。家族経営であれば夫婦、子供や親せきにお願いすることもできますが、身寄りの方がいない場合、アルバイトを雇ったりして作業をする必要があります。
※摘果・ラップ時に10日間アルバイトを1人雇う場合の目安です。およそ8万円
の費用が必要になります。
-

外張りビニール、マルチなど
栽培時に地面に貼るマルチやパイプハウスのビニールに必要になる費用です。パイプハウス用のビニールは、年々老朽化していくため、毎年交換が必要です。マルチは毎年交換し新しいものを利用する方が好ましく、生育環境づくりに大きく左右します。
※パイプハウスの修繕内容により費用は異なります。およそ80万円
の費用が必要になります。
-
定植苗の親株
15万円
-
肥料
20万円
-
農薬
20万円
-
光熱費
170万円
-
定植苗育苗用土
30万円
-
ミツバチレンタル
20万円
-
人件費
8万円
-
外張りビニール、マルチなど
80万円
※掲載している金額は目安です。
※10aの農地を基準に予算を掲載しております。
| 合計 | およそ 363万円 |
|---|
使える補助金
新規就農するときに、施設や機材の購入でおおきな資金が必要になってきます。ほとんどの人が事業用の融資を使っておりますが、就農1年目は収入のめどが立たず不安に思う人がとても多いです。
ここでは、移住するときや、研修期間中や設備購入費用や農業経営時に受けられる補助金の情報を、要件を満たす移住者を想定してお伝えします。【2024年5月現在】

●モデル家族構成
白石家(4人家族)- 父:白石たろうさん(35歳)
- 母:白石はなこさん(34歳)
- 息子:白石じろうくん(4歳)
- 息子:白石さぶろうくん(2歳)

●家賃補助・営農車補助(研修期間中)
-
住宅家賃の補助[初期費用と家賃※上限60,000円/毎月]
初期費用(家賃60,000円×3が上限) -
営農車の貸与[軽トラック、または軽バン]
※自家用車保有の場合貸与無し -
40リットル/毎月の燃料費支給 研修期間中の2年間
※(1)は町外から町内への移住者のみ
※(2)(3)は県外出身者のみ
| 合計 | 178万円 |
|---|
(住宅家賃補助・ガソリン代×2年分の合計の目安)

●就農準備資金(研修期間中)
-
新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の申請必要。
-
就農時に49歳未満の方が対象。
承認されれば年間最大150万円補助×2年間
※申請に漏れた場合、研修奨励金(JA独自事業)年間120万円×2年間(上記新規就農者育成総合対策の対象外の方のみ対象)を受けることができます。
| 合計 | 150万円/年間×2年間 |
|---|
(新規就農者育成総合対策が承認された場合)

●経営開始資金(就農開始時)
- 新規就農者育成総合対策経営開始資金[事前に青年等就農計画の認定が必要]
-
就農時に49歳未満の方が対象。
150万円/年間×最長3年間受給 - 夫婦ともに就農することが認められれば1.5倍の225万円/年間×3年間
| 合計 | 225万円/年間×3年間 |
|---|
(夫婦ともに就農することが認められた場合)


●経営発展支援事業(就農開始時)
- 補助率:国2分の1、県4分の1
- 支援額:補助対象事業費上限1,000万円
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円
※夫婦ともに就農することが認められれば1.5倍の1,500万円
(経営開始資金の交付対象者の場合は、補助対象事業費上限750万円)
※経営継承・発展支援事業との併用は不可。
また、他の国の助成事業の対象として整備するものではないこと。
| 合計 | 750万円 |
|---|
(夫婦ともに就農することが認められた場合かつ、
経営開始資金の交付者の場合です。)
●東京から移住して白石町で新規就農する
4人家族が受け取れる補助金・助成金
| 合計 | 5,503万円 |
|---|
ロールモデルの方の場合、およそ5,503万円ほどの補助金・助成金を受けることができます。
収入が不安定なスタートアップ時には、助成金を受けることで農業経営を軌道に乗せやすくなります。
農業開始後の農薬や肥料も高騰が進んでいますが、佐賀県露地野菜100億円アップ推進事業など補助事業もあり、安心して農業を続ける環境が整っています。